NO.1732 相加平均・相乗平均 2008.7.15 水の流れ
皆さん、教科書傍用問題集(数研出版)を見ていたら、相加平均・相乗平均の証明問題がでていました。
一部改題してあります。
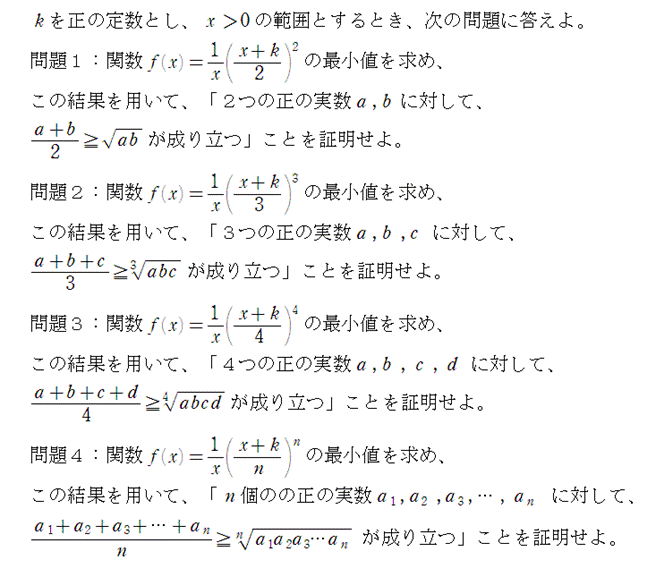
注:この記事に関する投稿の掲載は、2008年8月4日以降とします。
ColloquiumNO.233
|
皆さん、教科書傍用問題集(数研出版)を見ていたら、相加平均・相乗平均の証明問題がでていました。
一部改題してあります。
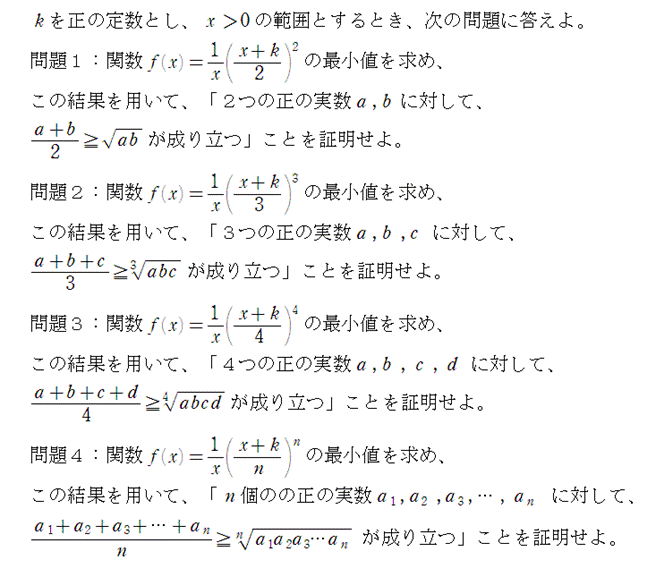
注:この記事に関する投稿の掲載は、2008年8月4日以降とします。
(1)
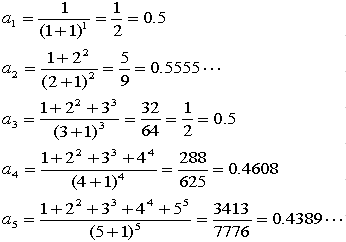
(2)
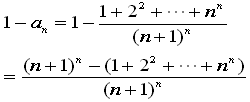
この式の分子の左の式は、二項定理で展開すると項が n+1 個です。
分子の右の式は、項が n 個です。
分母が正であるのは明らかなので、分子を 1 項ずつ比較して考えます。
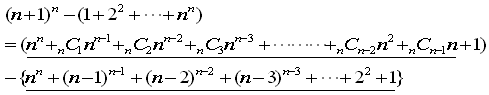
ここで上の式の下線部分(n個ずつ項があります)を考えます。
自然数の自然数乗の数については、指数が同じならば、底が大きい方が大きいことを
考えて、1つずつ比較します。
初めは同じですが、2個目以降は上にある方が底の部分が大きくてしかも二項係数があります。
しかも上の方は1のおまけまでついています。
だからこの差は正になり1の方が大きいことがいえます。
(3)
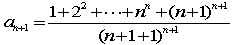
この関係式で右辺の分母を払い、両辺を(n+1)のn乗で割ります。
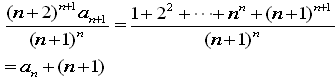
ここで第 n+1項について解くと
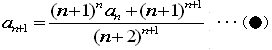
(4)
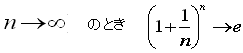
を意識しながら、(●)の式を変形します。
右辺の分子と分母をそれぞれnのn+1乗で割ってから変形をします。
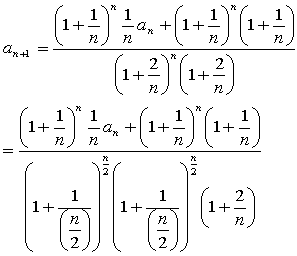
この数列が収束するとしてその値をαとしておきます。
n→∞ のときの様子を式にすると
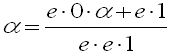
だから、
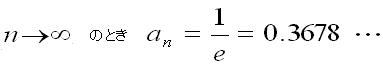
各項が等しく、かつ符号が等しい連続根号数の極限値を求めるのは簡単です。
それらは、コロキウム室NO.1622に書かれているように、
2次方程式を解く問題に帰着されます。
例えば、
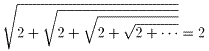
になります。
これに対して、各項が等しくても、符号が交替する連続根号数を求めるのは、
難しくなります。例えば、
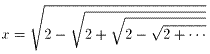
を求めるとします。この場合は、連立方程式
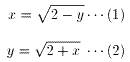
を考えます。(1)に(2)を代入すると
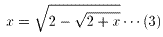
(3)を(3)自身に代入して、
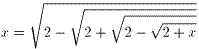
以下同様に、(3)に代入し続けると、
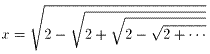
となります。よって求めるべき極限値xは、連立方程式(1)、(2)の解となります。
(1)、(2)より、
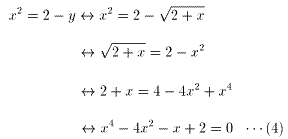
となり、したがってxを求めるには、(4)の4次方程式を解けばよいことがわかります。
(ただし、x>0 かつx≠2)
(4)の左辺を因数分解すると、
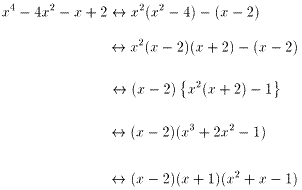
となり、2次方程式 x2+x−1=0(x>0)を解くと、
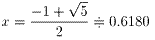
が求まります。故に、
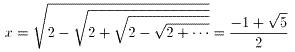
<追記>
上述の極限値は、各項が2だったからこそ、割合簡単に求められたのであって、
一般の場合はずっと難しくなると思います。
一般の四次方程式は、いわゆるフェラーリの公式を使って解くことができます。
しかし、解かれた結果得られる解の多くが、いわゆる「還元不能のパターン」になることが多く、
電卓で近似値を計算することができません。
§4.限定作用素をもつ理論
1.限定作用素の定義
§3.の論理的な理論では、文字xを含んでいる関係R(x)を仮定してSが導かれたならば、
R(x)⇒S(x)は、少なくともxが理論の定数でない限り、任意の対象xに対して成り立つと言えた。
S(x)とR(x)をつなぐ、恒真関係が存在するからだ。
それが論理的な理論のシェーマと三段論法だった。論理的な理論のシェーマS1〜S4と、
三段論法C1とは、任意の対象xに対して成立するところに、その特徴がある。
しかし、より一般的な状況では、そうでない恒真関係に基づく推論も用いられる。
例えば、R(x)が真だったとする。ふつうR(x)の真偽はxに依存する。
R(x)が成り立つのは、ふつう特定の対象xに対してだけである。
R(x)が、特定の対象xに対して成り立ったとしても、言える事は、
R(x)を成り立たせる対象xが少なくとも一つ存在する、という事だけだ。それでも、
R(x)が成り立つならば、R(x)を成り立たせる対象xが存在する.
は恒真関係と判断できる。この状況は、次のシェーマを認めるのと同じである。
S5 (T|x)R ⇒ (∃x)Rは、Tの公理.
ここでTはTの任意の対象式。S5の右辺を、「Rであるxが存在する」と読む事にする。
ところで、R(x)自体の成立の可否はxに依存するものの、
R(x)を成り立たせるxが存在するという事は、個々のxには依存しない事実である
(成り立つなら)。
従って(∃x)Rは、任意の対象を表す文字xを含まないように定義されるのが正しい。
この事を行えば、もし(∃x)Rが定理になったならば、任意の対象xを含まぬという意味で、
それが普遍的に真である事が形式的に保証されるので、
論理的な理論における恒真関係(命題理論として真な関係)として扱えるようになり、
§3の結果を全て含むようにできる。
これを行う直接的な方法は、R(x)を成り立たせる対象式そのもので、変数xを置き換える事だ。
ここではそれを、τx(R)と書く事にする。すなわち(∃x)Rは、記号列、
(τx(R)|x)R
の省略記法であると定義する。よって記号列τx(R)には、文字xが含まれてはならない。
しかしτx(R)は、R(x)の中のxに関連する対象であり、
しかもxがRの中の対象を表す文字である事も、直接的に示さなくてはならない。
そこで記号列τx(R)自体は、次の記号列の省略記法であると定義する。
文字xを含む記号列Rを、
R(・・・,x,・・・,x,・・・・・・,x,・・・)
としたとき、τx(R)とは、Rに含まれる文字xを全て同時に□で置き換え、
さらにτと□を、鎖といわれる記号で結んだものである。
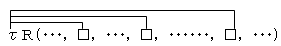
従って、τx(R)は文字xを含まない。
よって、(∃x)Rも文字xを含まない。
ただし、具体的なτx(R)の定義の仕方が、他にもたくさんあるのは明らかである。
以上の定義に従えば、S5は、
S5 (T|x)R ⇒ (τx(R)|x)Rは、Tの公理.
と同じになる。S5は、右辺は任意の対象を表すxを含めない恒真関係である。
そうすると、このタイプの関係をシェーマとして認めた場合、
R(x)⇒SやR⇒S(x)が導かれたからといって、
R(x)⇒S(x)は、必ずしも成り立たない事になる。
この違いは、少なくとも補助仮定の方法の適用に関して、
許される運用方法に、はっきりとした違いを与える。これについては後述するが、
その前に、(∃x)を利用して(∀x)を定義しておくと、議論が進めやすくなる。
意味からすると、τx(R)とは、Rを成り立たせる対象を表している。
そうすると、(τx(R)|x)Rは常に真ではないかと言いたくなる。しかしこれは、
S5' (∃x)Rは、Tの公理.
というシェーマを認めるのと同じであり、明らかにこれは出来ない。
何故なら、τx(R)が一つもないという、特別な場合があるからだ。
従ってτx(R)に、存在を主張する程の力はない事がわかる。
(∃x)R自体の成立の可否は、S5において、(T|x)Rが定理になるかどうかにかかっている。
そうではあるのだが、その特別な場合とは、
〜(∃x)R
のことであり、これは、
(∀x)(〜R)
に同じだと、判断される。形式的にはこれは、
(∀x)R ⇔ 〜(∃x)(〜R) ⇔ 〜(τx(〜R)|x)(〜R) ⇔ (τx(〜R)|x)R
とみなす事であり、τx(〜R)は、〜RでありかつRである対象なので、
空だとなる((∀x)Rが成り立つなら)。
すなわち、
(∀x)R ⇔ (τx(〜R)|x)R ⇔ τx(〜R)=φ
という意味にとる。「=φ」は説明の便宜上導入した。
よってτx(〜R)は存在せず、(∃x)(〜R)が成り立つ事はないという意味にとれる。
逆に〜(∃x)(〜R)が成り立つならば、(∀x)Rだと判断できる。
ところで、上の形式的定義を認めるならば、
(∀x)(〜R) ⇔ 〜(∃x)(〜〜R) ⇔ 〜(τx(〜〜R)|x)(〜〜R) ⇔ (τx(〜〜R)|x)(〜R)
を認める必要があるが、
(∀x)(〜R) ⇔ 〜(∃x)R ⇔ 〜(τx(R)|x)R ⇔ (τx(R)|x)(〜R)
と判断されて、形式上、2つの表式が一致しない。2つの表式が形式的にも一致するためには、
(τx(〜〜R)|x)(〜R) ⇔ (τx(R)|x)(〜R)
すなわち、
(τx(〜〜R)|x)R ⇔ (τx(R)|x)R
を保証する恒真関係が必要である。
状況を整理すると、次のようになる。(∀x)Rとは、
(∀x)R ⇔ 〜(∃x)(〜R)
の事なので、待遇をとれば、
〜(∀x)R ⇔ (∃x)(〜R)
となる。(∀x)Rの定義から導けるのは、これだけである。一方、逆の状況では、
〜(∃x)R ⇔ (∀x)(〜R)
が必要になる。これが成り立つためには、
〜(τx(〜〜R)|x)(〜〜R) ⇔ 〜(τx(R)|x)R
すなわち、
(τx(〜〜R)|x)R ⇔ (τx(R)|x)R
を示す必要がある。(∀x)Rの定義からは上記を導けない。上記関係は本質的に、
S5から導かれる(C29)。
〜(∀x)R ⇔ (∃x)(〜R)
〜(∃x)R ⇔ (∀x)(〜R)
を導いてしまえば、∃と∀は否定によって互いに移る事ができるようになる。
すなわち、(∀x)Rについての関係式を得たあとに、Rを〜Rに置き換えて対偶をとれば、
対応する(∃x)Rについての関係式が得られる。一方についての関係式があるなら、
他方についても同様であり、両者の全体は全く同等である。
ここまでは(∃x)Rと(∀x)Rの定義だけに関わる話である。
∃や∀を導入するのも、それらを用いて推論を行いたいからに他ならない。
従って∃,∀の運用と、証明の方法との整合性も確かめておく必要がある。
証明の方法には、「補助仮定の方法」,「帰謬法」,「場合分けの方法」,
「補助定数の方法」があったが、「補助仮定の方法」以外は本質的に、それから導けた。
従って「補助仮定の方法」だけを考慮する。
その際、∃と∀は否定によって互いに移り得るので、∀についてだけ考える。
なお§3.で行った論理的理論の内容は、命題理論と呼ばれる。
命題理論において、R(x)が定理になるとは、任意のxでR(x)が真となる事だった。
これは(∀x)Rが成り立つ事と同じであるが、R(x)を仮定する事と、(∀x)Rを仮定する事には、
重要な相違がある。R(x)が文字xをたまたま含まぬものなのか、
含んではいけないものなのかの違いである。
(∀x)Rを仮定する。(∀x)Rを仮定した理論においては、任意の対象xでR(x)が成り立つから、
命題理論の意味でR(x)は定理になるとみなせる。元の理論に戻っても、
(∀x)Rは、任意の対象xでR(x)が成り立つという意味だから、元の理論においても、
(∀x)R ⇒ R
は成り立つと判断できる。形式的には、(∀x)Rは文字xを含んでいない事から、
これが保証される。
以上の内容は、論理的な理論のシェーマS1〜S4から導ける内容ではないが、
S5をシェーマとする事により導ける(C30)。
次にR(x)を仮定してみる。R(x)を仮定した理論において、
R(x)は命題理論の意味において定理だから、理論の定数でない限りxは、
任意の対象を表し、(∀x)Rが成り立つとみなせる。しかし元の理論に戻った時に、
R(x)は任意の対象で成り立つとは限らない。つまり、
R ⇒ (∀x)R が成り立つとは限らない.
と判断できる。R(x)が任意の対象を表す文字xを含んでいるからだ。
形式的には、R ⇒ (∀x)Rを正当化する根拠はシェーマS1〜S4しかないが、
この推論はそれらと無関係に行われているので、形式的にもこれは恒真関係にならない。
(∀x)R ⇒ RもS1〜S4と無関係であるのは同様であるが、それが恒真関係になる
事はS5が保証する。よって、R ⇒ (∀x)Rが定理になるのは、(∀x)Rが元の理論
で定理になる時のみである。
特にR(x)が元の理論で定理であるなら、(∀x)Rも定理になる。
形式的にはR(x)が定理であるなら、xが理論の定数でない限り、
任意の対象で置き換えうるので、特にτx(〜R)で置き換えて(τx(〜R)|x)R、
すなわち(∀x)Rは定理になる。
あと必要なのは、これまでと同様に、∃と∀に関する分配則と交換則である。
これらがあれば、∃や∀を含んだ関係式を、要素関係式に分解できる。
分配則については、§3.5により、ouとetは否定で移り得るので、∀とetについて
考えれば十分である。これらは、C32とC34で行う。
C26
(∀x)R⇔(τx(〜R)|x)Rは定理。
[証明]
(∀x)R⇔(〜((∃x)(〜R))),(〜((∃x)(〜R)))⇔(〜(τx(〜R)|x)(〜R))
(〜(τx(〜R)|x)(〜R))⇔(〜〜(τx(〜R)|x)R),
(〜〜(τx(〜R)|x)R)⇔(τx(〜R)|x)R
は全て定理。従って、C22より、
(∀x)R⇔(τx(〜R)|x)R
は定理。
[証明終]
C27
Rを理論Tの定理、xを理論Tの定数でない文字とする。(∀x)Rは定理。
[証明]
Rが定理で、xが(理論Tの)定数でない文字だから、
(τx(〜R)|x)RはC3より定理である。C26より、
(τx(〜R)|x)R,(τx(〜R)|x)R⇔(∀x)R
は全て定理になり、
(∀x)R
は定理になる。
[証明終]
C28
〜(∀x)R⇔(∃x)(〜R)は定理。
[証明]
(∀x)R⇔(〜(∃x)(〜R))
であるが、対偶を取れば、
〜(∀x)R⇔(〜〜(∃x)(〜R)),〜〜(∃x)(〜R)⇔(∃x)(〜R)
である。従って、
〜(∀x)R⇔(∃x)(〜R)
[証明終]
2.限定作用素を持つ理論の公理
既述の論理的な理論のシェーマS1〜S4と、次に述べるシェーマS5
が非明示公理を与える全ての理論Tを、限定作用素を持つ理論と呼ぶ。
RはTの関係式、TはTの対象式とする。
S5 (T|x)R⇒(∃x)Rは、Tの公理.
3.限定作用素の性質
C29
〜(∃x)R⇔(∀x)(〜R)は定理。
[証明]
S5と限定作用素の定義より、
(τx(〜〜R)|x)R⇒(∃x)R,(∃x)R⇒(τx(R)|x)R
(τx(R)|x)(〜〜R)⇒(∃x)(〜〜R),(∃x)(〜〜R)⇒(τx(〜〜R)|x)(〜〜R)
が得られる。従って、
(τx(〜〜R)|x)R⇒(τx(R)|x)R
(τx(R)|x)(〜〜R)⇒(τx(〜〜R)|x)(〜〜R)
は定理である。最後の式の対偶を2回取れば、
(τx(〜〜R)|x)R⇒(τx(R)|x)R
(τx(R)|x)R⇒(τx(〜〜R)|x)R
が定理であることがわかる。すなわち、
(τx(R)|x)R⇔(τx(〜〜R)|x)R
は定理である。対偶を取れば、
〜(τx(R)|x)R⇔(τx(〜〜R)|x)(〜R)
となり、限定作用素の定義から、
〜(∃x)R⇔(〜(τx(R)|x)R),
〜(τx(R)|x)R⇔(τx(〜〜R)|x)(〜R),
(τx(〜〜R)|x)(〜R)⇔(∀x)(〜R)
が得られる。従って、
〜(∃x)R⇔(∀x)(〜R)
は定理。
[証明終]
C30
(∀x)R⇒(T|x)Rは定理。
[証明]
S5と限定作用素の定義より、
(T|x)(〜R)⇒(∃x)(〜R),(∃x)(〜R)⇒(τx(〜R)|x)(〜R)
は定理である。従って、
(T|x)(〜R)⇒(τx(〜R)|x)(〜R)
は定理。対偶を取れば、
(τx(〜R)|x)R⇒(T|x)R
が定理となり、これは、
(∀x)R⇒(T|x)R
と同じ。
[証明終]
C31
文字xが定数でないとする。R⇒Sが定理なら、(∀x)R⇒(∀x)Sと(∃x)R⇒(∃x)Sは定理。
[証明]
C30と問題の前提から、
(∀x)R⇒R,R⇒S
は定理で、
(∀x)R⇒S
は定理になる。ここで(∀x)Rを仮定すれば、Sが定理となり、xは定数でないから、
C27を考慮して一連の証明、
(∀x)R,(∀x)R⇒S,S,(∀x)S
が得られる。従って、補助仮定の方法より、
(∀x)R⇒(∀x)S
は定理である。次にR⇒Sの対偶
(〜S)⇒(〜R)
を考え、上記で証明したことを適用すれば、
(∀x)(〜S)⇒(∀x)(〜R)
は定理である。C29より、
〜(∃x)S⇒(∀x)(〜S),(∀x)(〜S)⇒(∀x)(〜R),(∀x)(〜R)⇒(〜(∃x)R)
なので、
(〜(∃x)S)⇒(〜(∃x)R)
は定理である。もう一度対偶をとることにより、
(∃x)R⇒(∃x)S
が定理になる。
[証明終]
C32
(∀x)(RetS)⇔((∀x)Ret(∀x)S)
(∃x)(RouS)⇔((∃x)Rou(∃x)S)
は定理。
[証明]
C30から、
(∀x)(RetS)⇒RetS
は定理である。ここで(∀x)(RetS)を仮定すれば、RetSが定理となり、一連の証明、
(∀x)(RetS),(∀x)(RetS)⇒RetS,RetS,R,S,(∀x)R,(∀x)S,(∀x)Ret(∀x)S
が得られるので、
(∀x)(RetS)⇒RetS,RetS⇒((∀x)Ret(∀x)S)
すなわち、
(∀x)(RetS)⇒((∀x)Ret(∀x)S)
は定理である。逆に、(∀x)Ret(∀x)Sを仮定すれば、一連の証明、
(∀x)Ret(∀x)S,(∀x)R,(∀x)S,(∀x)R⇒R,(∀x)S⇒S,R,S,RetS,(∀x)(RetS)
が得られる。従って、
((∀x)Ret(∀x)S)⇒(∀x)(RetS)
は定理である。すなわち、
(∀x)(RetS)⇔((∀x)Ret(∀x)S)
は定理である。
次に、いま証明したことから、
(∀x)((〜R)et(〜S))⇔((∀x)(〜R)et(∀x)(〜S))
は定理である。また、
((〜R)et(〜S))⇔(〜(RouS))
は定理である。従ってxが定数でなければ、C31とC29より、
(∀x)((〜R)et(〜S))⇔(∀x)(〜(RouS)),(∀x)(〜(RouS))⇔(〜(∃x)(RouS))
から、
(∃x)(RouS)⇔(〜(∀x)((〜R)et(〜S)))
は定理となる。同様にC29より、
(∀x)(〜R)⇔(〜(∃x)R),
(∀x)(〜S)⇔(〜(∃x)S),
が得られるので、
((∀x)(〜R)et(∀x)(〜S))⇔((〜(∃x)R)et(〜(∃x)S))
((〜(∃x)R)et(〜(∃x)S))⇔(〜((∃x)Rou(∃x)S))
は定理である。よって、
〜((∀x)(〜R)et(∀x)(〜S))⇔((∃x)Rou(∃x)S))
は定理になる。以上まとめれば、
(∃x)(RouS)⇔(〜(∀x)((〜R)et(〜S))),
〜(∀x)((〜R)et(〜S)))⇔(〜((∀x)(〜R)et(∀x)(〜S))),
〜((∀x)(〜R)et(∀x)(〜S))⇔((∃x)Rou(∃x)S))
が定理となる。これらは、
(∃x)(RouS)⇔((∃x)Rou(∃x)S))
を意味する。
[証明終]
次の関係式は、一般的には成り立たない(意味を考えても)。
(∀x)(RouS)⇔((∀x)Rou(∀x)S)
(∃x)(RetS)⇔((∃x)Ret(∃x)S)
C32が成り立つ根拠は、
(∀x)(RetS),(∀x)(RetS)⇒RetS,RetS,R,S,(∀x)R,(∀x)S,(∀x)Ret(∀x)S
と分解できる事だったが、RouSに同様な分解を試みると、本質的に場合分けの方法になるので、
(∀x)(RouS),(∀x)(RouS)⇒RouS,RouS,
R ⇒ RouS,S ⇒ RouS,RouS,(∀x)(RouS)
となり、
(∀x)(RouS)⇒(∀x)(RouS)
しか導けない。しかし次の関係式は明らかに成り立つ(意味を考えても)。
((∀x)Rou(∀x)S)⇒(∀x)(RouS)
(∃x)(RetS)⇒((∃x)Ret(∃x)S)
また、次の事も導ける。
C33
文字xが、Rの中に現れないとする。次は定理である。
(∀x)(RouS)⇔(Rou(∀x)S)
(∃x)(RetS)⇔(Ret(∃x)S)
[証明]
(∀x)(RouS)⇒(RouS)
は定理である。ここで(∀x)(RouS)を仮定すれば、Rがxを含まぬことより一連の証明、
(∀x)(RouS),(∀x)(RouS)⇒(RouS),RouS,(τx(〜S)|x)(RouS),
(τx(〜S)|x)(RouS)⇒(Rou(τx(〜S)|x)S),(Rou(τx(〜S)|x)S)⇒(Rou(∀x)S)
が得られる。従って、
(∀x)(RouS)⇒(Rou(∀x)S)
は定理。逆に、Rou(∀x)S,R,(∀x)Sを仮定すれば、
Rou(∀x)S,(∀x)S,(∀x)S⇒S,S,R,R⇒RouS,S⇒RouS,(∀x)(RouS)
は定理になる。従って、場合分けの方法より、
(Rou(∀x)S)⇒(∀x)(RouS)
は定理。よって、
(∀x)(RouS)⇔(Rou(∀x)S)
が定理となる。いま証明したことより、
(∀x)((〜R)ou(〜S))⇔((〜R)ou(∀x)(〜S))
は定理。従って、
(∀x)(〜(RetS))⇔(〜(Ret(∃x)S))
(〜(∃x)(RetS))⇔(〜(Ret(∃x)S))
(∃x)(RetS)⇔(Ret(∃x)S)
が得られ、最後の関係は定理になる。
[証明終]
C34
(∀x)(∀y)R⇔(∀y)(∀x)R
(∃x)(∃y)R⇔(∃y)(∃x)R
(∃x)(∀y)R⇒(∀y)(∃x)R
は定理。
[証明]
(1) (∀x)(∀y)R⇔(∀y)(∀x)R
証明、
(∀x)(∀y)R,(∀x)(∀y)R⇒(∀y)R,(∀y)R,(∀y)R⇒R,R,(∀x)R,(∀y)(∀x)R
を考えれば、
(∀x)(∀y)R⇒(∀y)(∀x)R
が得られる。次に証明、
(∀y)(∀x)R,(∀y)(∀x)R⇒(∀x)R,(∀x)R,(∀x)R⇒R,R,(∀y)R,(∀x)(∀y)R
を考えれば、
(∀y)(∀x)R⇒(∀x)(∀y)R
が得られる。従って、
(∀x)(∀y)R⇔(∀y)(∀x)R
は定理。
(2) (∃x)(∃y)R⇔(∃y)(∃x)R
(1)より、
(∀x)(∀y)(〜R)⇔(∀y)(∀x)(〜R)
は定理。従って、
(∀x)(〜(∃y)R)⇔(∀y)(〜(∃x)R)
(〜(∃x)(∃y)R)⇔(〜(∃y)(∃x)R)
(∃x)(∃y)R⇔(∃y)(∃x)R
が得られる。最後の関係が、証明しようとしていたもの。
(3) (∃x)(∀y)R⇒(∀y)(∃x)R
(∀y)R⇒R,R⇒(∃x)R,(∀y)R⇒(∃x)R
より、
(∀y)R⇒(∃x)R
は定理である。(∃x)Rがxを含まぬことより、
(∃x)(∀y)R⇒(∃x)R
は定理。ここで(∃x)(∀y)Rを仮定すれば、一連の証明、
(∃x)(∀y)R,(∃x)(∀y)R⇒(∃x)R,(∃x)R,(∀y)(∃x)R
が得られる。従って、
(∃x)(∀y)R⇒(∀y)(∃x)R
は定理。
[証明終]
次の関係式は、一般的には成り立たない(意味を考えても)。
(∀y)(∃x)R⇒(∃x)(∀y)R
C34で逆の関係式が成り立つのは本質的に、
(∀y)R ⇒ R ⇒ (∃x)R
が成り立つからである。(∀y)(∃x)Rに同様な導出を試みると、
R ⇒ (∀y)R ⇒ (∃x)(∀y)R
を認める必要に迫られる。これは、この節の冒頭で述べたように不可である。
