| NO.1542 | 2005.7.4. | 佐野允信 | 放物線の長さ(2) |
問題2
求める放物線の長さを とすると
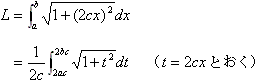
と表せる。
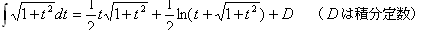
より
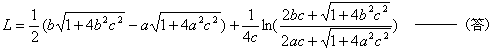
問題1
問題2の結果に,a=0,b=1,c=1 を代入すればいい.
よって、求める放物線の長さは,
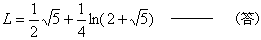
(補足)
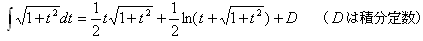
を示す。
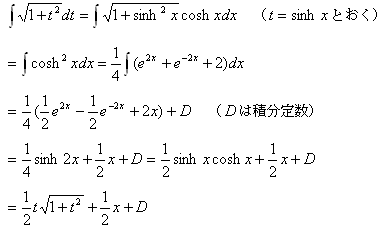
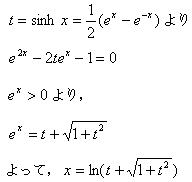
したがって,
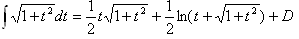

| NO.1543 | 2005.7.4. | 夜ふかしのつらいおじさん | 放物線の長さ(3) |
問題1:
(1/4)log_e(2+√5)+(√5)/2≒1.47894・・・
問題2:
(1/4c)loge{(2cb+√(4 c2 a2+1))/(2ca+√(4 c2 a2+1))}
+1/2 {b √(4 c2 b2 + 1)−a√(4 c2 b2 + 1)}
まず、放物線y=cx2の原点Oから点A(a,ca2)の長さを求めます。
放物線にそった微小変量をdsとします。
曲線の長さをLとすると、
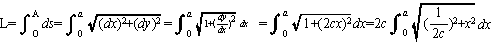
ここで、x=(1/2c)tanθ と置く。
すると、dx=(1/2c)・1/(cosθ)2・dθ、
x:0→a から θ:0→α(ただし、tanα=2ca)なので、
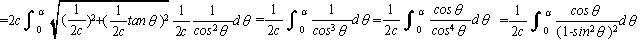
ここで、sinθ=t と置く。
すると、cosθ dθ=dt 、
θ:0→α から t:0→T(ただしT=2ca/(√(4 c-2 a2+1)))

この(A)の式で、c=a=1とすると、問題1、この式(A)のaをbに変えたものから(A)を引くと問題2の解答が得られます。

| NO.1544 | 2005.7.4. | 蜘蛛の巣城 | 放物線の長さ(4) |
ひょっと解いてみる気になりました。
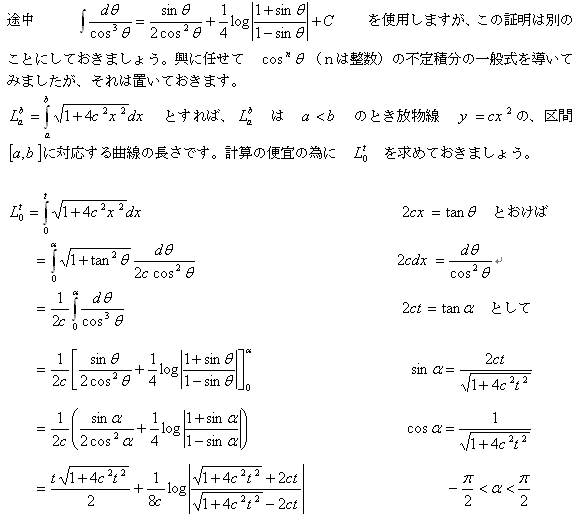
得られた値は c の符号の反転に影響は受けません。(当然ですね。でなきゃ困ります)
さて、a<bのとき
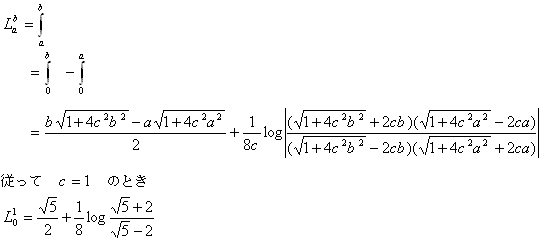

| NO.1545 | 2005.7.4. | 水の流れ | オイラー関数 |
皆さん、オイラー関数って知っていますか。今回はこの性質を利用しながら考えてください。
「オイラー関数」
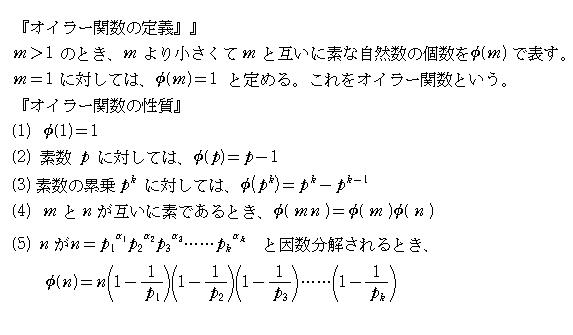 |
問題1
(1)φ(n)=8を満たす自然数nを求めよ。
(2)φ(n)=20を満たす自然数nを求めよ。
問題2:
100より小さくて、100と互いに素なすべての自然数Mについて
(1)この自然数Mの個数を求めよ。
(2)この自然数Mの和を求めよ。
問題3:
(1)20のすべての正の約数dについて、φ(d)の値を合計するといくつか。
(2)100のすべての正の約数dについて、φ(d)の値を合計するといくつか。
(3)一般に、自然数nのすべての正の約数dについて、φ(d)の値を合計するといくつか。
注)この記事に関する投稿の掲載は、7月24日以降とします。

| NO.1546 | 2005.7.23. | DDT | 根空間への分解定理 |
1.根空間への分解定理
ここでいう根空間とは、ベクトル空間の中で定義される次のような部分空間です。ベクトル空間Vの次元を、
線形変換A(行列A)を、
として、
で定義されるベクトルx∈Vの全体Viのことです。ここでλiは、一般的にはある体の要素であり、EはAと同じ次元の単位行列で、miとnは0以上の整数 mi≦nです。これを、
と表します。Viが、固有値λiに属する高さのmiの根空間Viです(mi=1なら固有空間)。「根空間への分解定理」とは、次の定理をさします。
定理1.(根空間への分解定理)
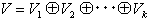
が成り立つ。ここで(Vi)i=1〜kは、固有値λiに属する高さのmiの根空間Viであり、
m1+m2+・・・+mk=n
となる。ただしは、部分空間の直和を表す。
定理1.は固有ベクトル空間への分解定理の原型であり、線形代数を使って、何故固有ベクトルを計算するかの動機付けを与えるものです。かつこの定理は、初等線形代数の一つの山場であるはずです(陰関数定理が、初等解析の山場であるように)。
定理1.は通常、次の三つの前提から導かれると思います。
1) Cayley-Hamiltonの定理.
2) 互いに素な消去多項式の核空間の独立性.
3) ユークリッドの互除法.
定理1.は初等線形代数の山の一つであるはずなのに、1)〜3)を前提とすると、その証明が全然「線形代数っぽくない」というのがここでの趣旨です。ここには個人的な偏見が存在しています。その偏見とは、
(偏見a)
というものです。上記偏見に従うと1)〜3)には、一般代数系からの密輸入があり過ぎるような気がします。ただし線形代数も代数なので、ある程度の一般代数系の知識は必要です。
そこで、最低限の一般代数系からの密輸入だけで定理1.を証明できないか?という話です。結論は、以下となりました。
1) Cayley-Hamiltonの定理(天下りに認める!。この定理は線形代数の外にある!).
2) 互いに素な消去多項式の核空間の独立性(簡単なので、これくらいは認める).
3) 後は、ベクトルの線形性だけで片付ける.ユークリッドの互除法は不要!.
以下、順番に様子をみてみます。
2.Cayley-Hamiltonの定理
Cayley-Hamiltonの定理は、高校数学でも半分おなじみのものだと思います。
それは、行列A(線形変換A)の特性多項式を、
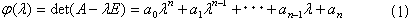
とした場合、形式的にλをAにおきかえたψ(A)が実は、
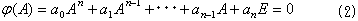
になるという定理です。この証明は初等的には以下となります(「線形代数,伊里正夫,韓大舜,1979年,教育出版株式会社」を使いました)。まず行列 A−λE の随伴行列 agj(A−λE)を、
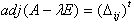
で定義します(tは転置)。ここでΔijは、δijをクロネッカーのデルタとして、
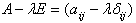
の成分 aij−λδij の余因子です。余因子の定義より、agj(A−λE) の成分は、λの(n-1)乗以下の多項式です。よってagj(A−λE) は、A0〜An-1を適当な定数行列(λを含まない)として、
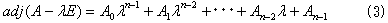
と表せます。一方、行列式のラプラス展開を考慮すると、
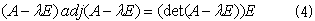
となるので(クラーメルの公式のもと)、(1)と(3)より、
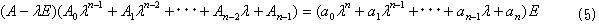
となり、式(5)の両辺でλiの係数行列を比べると、
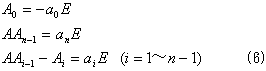
が得られます。(6)を漸化式と考えて順番に代入して行くと、最後には(2)に達する(証明終)。 以上が初等的な(狭義の線形代数の範囲内での)Cayley-Hamiltonの定理の証明の粗筋ですが、これでは「何故かわからいが漸化式を作ってみたら、(2)に達してしまった」としか言えないと思います。ここで「狭義の線形代数」とは、足が3本以上立つテンソル解析を含まないという意味です。もちろん狭義の線形代数においても行列式計算(交代化演算)は必須ですから、「ラプラス展開を考慮する」ことは正当ですし、漸化式(6)を作る動機付けも、ラプラス展開を考慮した関係(4)が成り立つので「やってみるのも悪くない」とは言えます。しかし「偏見(a)」を満たしてくれません。
交代化演算は結局多重線形関数なんだから「偏見(a)」を満たしてるじゃないかと言われれば、それまでなのですが、少なくとも(1)〜(6)には行列やベクトルの線形性が陽に現れていません。また、次の偏見(b)にも抵触します。
(偏見b)
つまり、もし漸化式(6)を作るなら、その動機付けが完璧でなければ嫌です(← 我がままだ!)。「やってみるのも悪くない」くらいでは納得できません。個人的には、狭義の線形代数の内部で、ついにこれは解決できませんでした。
後日難しい代数系の本を斜め読みした結果では、Cayley-Hamiltonの定理は、
1) スカラー上の多項式環(特性多項式) 2) 行列多項式環(Cayley-Hamiltonの定理)
の間の準同型対応から直接出てくるような印象を受けました。図-1が、その準同型対応の概略です。図-1の詳細がわかっていると、Cayley-Hamiltonの定理はある準同型定理の系として、「ポン!」と出てくる(らしい)。この時には、漸化式(6)を作る動機付けも完璧になっている。これは、一般代数系までいってみて初めて手に取るようにわかる、ことを意味します。というわけで、Cayley-Hamiltonの定理は、狭義の線形代数の外にあると思います。なので「天下りに認め」て「これ以上は関りません」。
(でもどなたか、手に取るような証明を教えてください。お願いします)
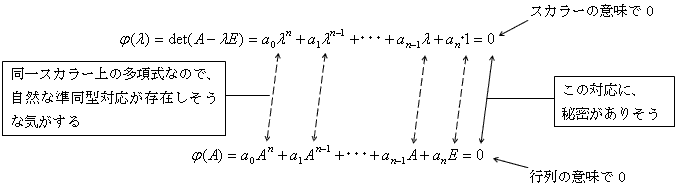
図-1 特性多項式とCayley-Hamiltonの定理の準同型対応の概略
2.互いに素な消去多項式の核空間の独立性
まず核空間を定義します。核空間とは、ベクトル空間VからV'への線形写像(行列)、
に対して、
となるx∈Vの全体ker(A)のことです。ker(A)は明らかにVの部分空間で、行列Aの性質だけからその全体が決まります。そこでker(A)のことを、Aの核空間と呼びます。
次にベクトルx∈Vを0に変換する行列Aの多項式を、ベクトルxに関する行列Aの消去多項式と呼びます。いま例えば、
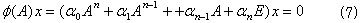
としたとき、行列多項式 φ(A)にAをかけたA・φ(A)においても、A・φ(A)x = A・0 = 0は明らかです。よって消去多項式の次数は、一般に一意には定まりません。そこで最小消去多項式を次のように定義します。
定義1.(最小消去多項式の定義)
式(7)を満たす行列多項式φ(A)のうち最低次数であるものを、ベクトルxに関する行列Aの最小消去多項式と呼び、
で表す。 ベクトルxの消去多項式と最小消去多項式の関係は以下です。
補題1.
ベクトルxの最小消去多項式は、同一ベクトルに対する任意の消去多項式を割り切る。ここで割り切るとは、スカラー上の多項式における割り切る、割り切らない(余りが出る)と同じ意味。
[証明]
ベクトルxの最小消去多項式と消去多項式を、それぞれφmin(A),φ(A)とする。
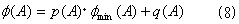
とかける。ここでp(A)はφmin(A)とφ(A)をAに関する多項式と考えて、φ(A)をφmin(A)で割った商で、ある適当な行列Aの多項式。q(A)はその余りで、やはり行列Aの多項式。q(A)の次数がφmin(A)の次数より低いことは明らか(φmin(A)で割った余りだから)。
式(8)より、
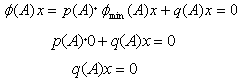
が導ける。ここでq(A)≠0(零行列)とすると、最小消去多項式φmin(A)よりも次数の低い、ベクトルxの消去多項式が存在することになる。これは最小消去多項式の定義に反する。よってq(A)=0であるか、x=0が必要。
1) q(A)=0の場合、最小消去多項式φmin(A)は、φ(A)を割り切る。 2) x=0の場合、xの最小消去多項式が単位行列Eのスカラー倍であることは明らか。従っていずれにしろ、最小消去多項式は、同一ベクトルに対する任意の消去多項式を割り切る。
[証明終]
補題1.から次の補題2.をすぐに得ます。
補題2.
互いに素な行列多項式の核空間は独立。ここで互いに素とは、互いに互いを割り切らない多項式の意味。
[証明]
φ1(A),φ2(A)を行列Aの多項式として、その核空間を、
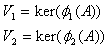
とする。x≠0かつx∈V1∩V2とすると、φ1(A)とφ2(A)はベクトルxの消去多項式になっているから、共通因数として最小消去多項式φmin(A)を含む。Ex≠0は明らかだからφmin(A)≠Eも明らか。よってφ1(A)とφ2(A)が互いに素なら、V1∩V2={0}が必要。これはV1とV2が独立な部分空間であることを意味する。
[証明終]
3.線形写像の標準(?)分解(後はベクトルの線形性のみ.ユークリッドの互除法は使わない)
根空間への分解定理を証明するために、あと定義4つと補題を3つ追加します。いずれも簡単なものです。
定義2.(線形写像と線形変換の用語上の区別)
VとV'を、必ずしも同一とは限らないベクトル空間とする。写像A(行列A)が、
A:V → V’
で線形であるとき、これをVからV'への線形写像という。とくにV'=Vであるとき、V上の線形変換と呼ぶ。
定義3.(正則線形写像の定義)
VからV'への線形写像A(行列A)が単射(1対1対応)であるとき、正則と呼ぶ。
定義3.から、次の補題がほぼ自明に出ます。
補題3. 線形な A:V→V'が正則である条件は、
ker(A)={0}
が成り立つこと。
[証明]
A・0=0は明らか。0∈V'に写像するx∈V全体とは、ker(A)のこと。Aは正則なので単射。よって、A・0=0より、ker(A)={0}である。
逆にker(A)={0}とする。xとy∈Vとして、Ax=Ayとすれば、
Ax−Ay=0
A(x−y)=0
となるので、
でなければならない。これは、
x=y
を意味する。従ってAは単射であり、正則。
[証明終]
定義4.(像空間という用語の定義)
Aを、VからV'への線形写像(行列)とする。x∈Vとして、Ax∈V'のことを、Aによるxの像と呼ぶ。xをVの中で任意に動かした時のAxの全体の集合、
のことを、AによるVの像と呼び、AVで表す。AV⊂V'は、V'の部分空間をなす。AVを、Aの像空間と呼ぶ。
定義5.(写像の実質部分)
XとYを集合、fを写像(線形でなくても良い)、
とする。定義4.と同様に、ここでも、f(x)をfによるx∈Xの像と呼ぶ。f(x)の全体、
のことを、fによるXの像と呼び、f(X)で表す。f(X)⊂Yは明らか。
ところで、Yに関するf(X)の補集合 Y−f(X) の中には、fでXから写像してくるものはない。従って、fの値域Yをf(X)に狭めても、実質的にfは変わらないことになる。
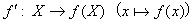
で定義される写像f'のことを、f(X)への移行によってfから得られる写像という。
次に、Z⊂Xの場合も用語を流用して、x∈Zのfによる像f(x)の全体のことを、やはりf(Z)と書く。f(Z)⊂f(X)⊂Y。このとき、fの定義域XをZに狭めて得られる写像f"、
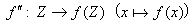
のことを、やはり用語を流用して、Zとf(Z)への移行によってfから得られる写像という。
線形写像の基本構造は、補題4.となる。
補題4.(線形写像の基本構造)
A:V→V'を線形写像、Vに関するker(A)の直和補空間を W とする。Wと、AによるWの像AW への移行によってAから得られる写像、

をA'で表す。A'に関して以下が成り立つ。
1) ker(A)の直和補空間 W は必ず存在する。従ってA'も必ず存在する。
2) A'は線形写像。従ってAW は V' の部分空間。
3) A'は正則線形写像。
4) Wの基底は、AWの基底に写る。
5) AW=AV。
6) 逆線形写像(逆行列)A'-1、
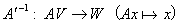
が存在する。
[証明]
1)
ker(A) はVの部分空間だからベクトル空間であり、ker(A)を張る基底Bkerが必ず存在する。ただし、Bker={0}の場合も基底と約束する(これはker(A)={0}を意味し、その場合Aは正則である)。
Bkerの全てのベクトルと独立で、しかも互いに独立なベクトルを、Vの中から最大本数集めてきて、それをBWとすれば、BWはある部分空間Wの基底であり、Wの中の全てのベクトルと、ker(A)の中の全てのベクトルは独立になる。またBW∪Bkerは、明らかにVの基底である。これらは、

と、
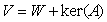
を意味し、
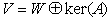
であることが言える。ただし、BW={0}の場合も基底と約束する(これはker(A)=Vを意味し、その場合はA=0である)。従って、ker(A)の直和補空間 W は必ず存在し、A'も必ず存在する。
2)
AW⊂AV⊂V' が V' の部分空間であるためには、A' が線形写像であれば良い。A'の定義より、x,y∈W、kをスカラーとすれば、
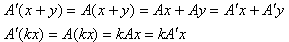
だから、A'は線形写像。
3)
2)より、A'は線形写像だからker(A')は意味を持ち、やはりA'の定義より、
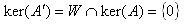
が成り立つ。補題3.より、A'は正則。
4)
BW={w1,w2,・・・.wk}をWの基底とする。
任意のx∈Wは、αi(i=1〜k)をスカラーとして、
と書ける。
である。定義5.の最後よりA'は全射だったから、AWの任意のベクトルは、式(9)の形をしていなければならない。 これは BAW={Aw1,Aw2,・・・,Awk} で AW が張られることを意味する。 ただし、BAW のベクトルが全て互いに独立であることは、ただちに明らかではない。次にこれを示す。
とすると、右辺の0が0∈AWなのは自明だから、
より、
でなければならないが、3)よりA'は正則で、ker(A')={0}。従って、
となる。BW={w1,w2,・・・.wk}はWの基底だったから、αi=0(i=1〜k)となる。 これは、BAW={Aw1,Aw2,・・・,Awk} のベクトルが全て互いに独立であること意味する。 よって BAW は AWの基底であり、BW がWの基底なら、BAW はAWの基底。
5)
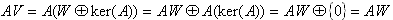
だから。
6)
5)より、AW=AVなので、
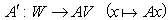
である。線形写像A'は明らかに全射で、3)より単射だった。従ってA'は双射(1対1かつ上への写像)であり、逆写像、
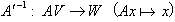
が存在する。これが線形であれば良い。Ax,Ay∈AVとすると、逆写像の定義より、
が成り立つが、A'の定義から、A'-1(Ax)=x,A'-1(Ay)=yでもあるから、
がいえる。同様にkをスカラーとして、
から、
がいえる。よって逆写像A'は線形。
[証明終]
補題4.は、次の図-2としてまとめられる。図-2を、線形写像Aの標準分解と呼ぶ(と勝手に呼んでます)。 図-2をとくにV'=Vで、AがV上の線形変換 A:V→V の場合で考えると、次の補題5.が得られる。
補題5.
A:V→Vを線形変換とする。Vが有限次元の場合、次の3つは同値である。
1) Aが正則[証明] 1) ⇔ 2)
2) Aが単射
3) Aが全射
定義3.そのもの。
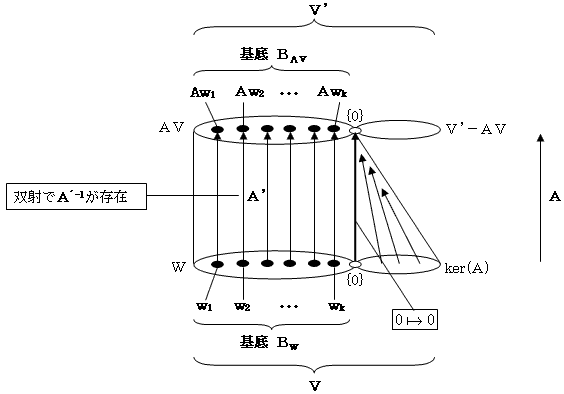
図-2 線形写像の標準分解
1) ⇒ 3)
Aが正則なら、補題3.よりker(A)={0}。これは図-2で、V'=V,W=VかつA'=Aとなった場合に相当する。A'はもともとAVへの全射だったから、AV=Vであれば良い。図-2より、それはAVの基底BAV がV'を張ることを意味する。
補題4.の4)より、Wの基底BW は AVの基底BAV に写るが、W=Vであることから、BW はVの基底BV である。
BV に含まれるベクトルの本数とは、Vから集めてこれる独立なベクトルの最大本数のこと(それが基底と次元の定義)。
BAV に含まれるベクトルの本数は、BV に含まれるベクトルの本数に等しい。
いまV'=Vに注意すると、BAV に含まれるベクトルの本数は、V'=Vから集めてこれる独立なベクトルの最大本数に等しい。よってBAV はV'=Vの基底である。これは、Vの部分空間AV⊂Vの基底BAV が、Vを張ることを意味するから、AV=Vとなる。従って、Aは全射。
3) ⇒ 1)
Aが全射なら、図-2でAV=V'=Vだから、逆線形変換、
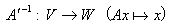
が存在する。逆線形変換も線形写像だから、A'-1用に図-2を書きなおすと、図-3となる。
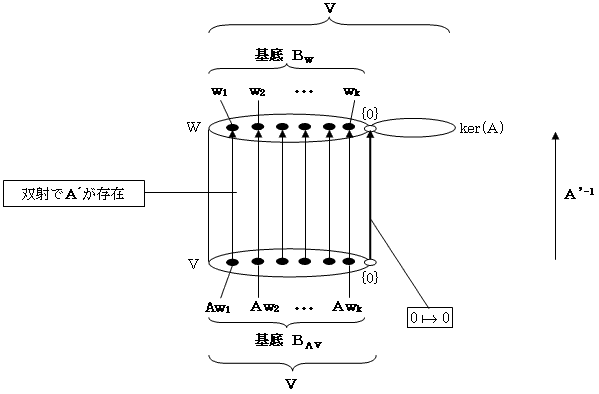
図-3 線形写像の標準分解
図-3と図-2を比較すると、さっきと同様に基底BW がVを張るのは明らかだから、ker(A)={0}である。補題3.より、Aは正則で単射(お釣りとして、A'=A)。
[証明終]
以後使用しないが、図-2からは、次の系1.があっさりと出てくる。これも有限次元の線形代数(つまりふつうの線形代数)の基本定理の一つと思えるが、何故か余り注目されません。実際、次元や基底の定義を思い出すと、系1.は、図-2や補題4.と同値です。
系1.
A:V→V'を線形写像とする。Vが有限次元の場合、次式が成り立つ。
[証明]
図-2より自明。
[証明終]
4.根空間への分解定理の証明
ここで「根空間への分解定理」をもう一度まとめる。次元nのベクトル空間V上の行列A(線形変換A)の特性多項式が、
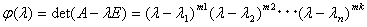
であるとき(m1+m2+・・・+mk=n)、 ψ(λ)のλを形式的にAに置き換えたψ(A)において、Cayley-Hamiltonの定理、
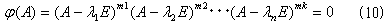
が成り立ち、全空間Vは、(A−λiE)miの核空間である根空間Vi、
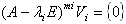
によって、直和分解、
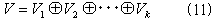
をうけるというものです。
ここで全空間Vは、特性多項式ψ(A)の核空間になっています。また根空間Viは、ψ(A)の因子である行列多項式(A−λiE)miの核空間で、各(A−λiE)miは互いに素な行列多項式なので、 V1〜Vkは最初から独立な部分空間になっています(補題2.)。 さらに因子(A−λiE)miも、A上の線形変換で、かつ可換なのは明らかです。これらの言葉で(10)と(11)を書き直すと、AiをV上の線形変換として、
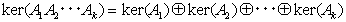
が成り立ち、式(12)が成り立つ条件は、線形変換Aiが互いに可換で、Aiの核空間ker(Ai)が互いに独立というものです。「根空間への分解定理」を証明するためには、結局次の補題が成り立てば良いことがわかります。
補題6.
A1とA2をV上の可換な線形変換で、核空間が独立とする。すなわち、

とする。このときA1A2の核空間を、
とすれば、

[証明]
A1とA2が可換だから、
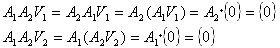
が成り立ち、V1,V2⊂V0で、V1とV2はV0の部分空間をなす。 よってV0の中での V1+V2 の直和補空間が存在する。それをV3とする。 V1とV2はもともと独立なので、
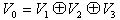
となる。V3={0}がいえれば良い。 A1とA2が可換であることより、
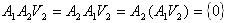
なので、
でなければならない。すなわち、A1はV2上の線形変換になっている。
同様に、
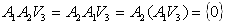
なので、
でなければならない。よってA1は、V3からV2への線形写像も定義するが、これと(13)を合わせると、 A1は、V23V3からV2への線形写像にもなっている。
V2への移行によってA1から得られる線形写像を考え、 これをA1(2)と表す。(13)より、A1(2)はV2上の線形変換、
になる。A1(2)の核空間は明らかに、 A1の核空間V1とV2との共通分だが、 これらはもともと独立だったので、
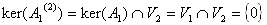
である。従ってA1(2)はV2上で正則(補題3.)なので全射(補題5.の3))。よって、
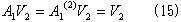
が成り立つ。 次に、V2
 V3への移行によってA1から得られる線形写像を考え、これをA1(2+3)と表す。(13)と(14)より、これはV2
V3への移行によってA1から得られる線形写像を考え、これをA1(2+3)と表す。(13)と(14)より、これはV2 V3からV3への線形写像、
V3からV3への線形写像、
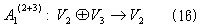
となり、その核空間は、A1(2)の場合と同様に、
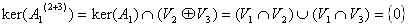
である。A1(2+3)は正則であり、独立なベクトルは独立なベクトルに写像されるので(補題4.の4))、
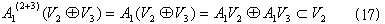
が成り立つ。A1V2⊂A1VSUB>2
 A1V3は明らかであるから、(17)より、
A1V3は明らかであるから、(17)より、
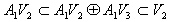
である。(15)を考慮すると、
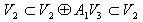
となって、
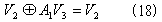
が得られる。(18)から明らかに、A1V3={0}なので、
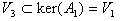
が得られる。A2とV3に関しても、(19)と同じ関係が得られるので、
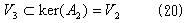
でなければならない。(19)と(20)より、

となり、V3={0}
[証明終]
定理1.(根空間への分解定理)
次元nのベクトル空間V上の線形変換になっている行列Aの特性多項式を、
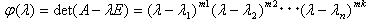
とする(m1+m2+・・・+mk=n)。 ベクトル空間Vは、高さmiの固有値λiに属する根空間Vi、
によって、直和分解、
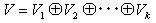
を受ける。ただし
 は、部分空間の直和を表す。
は、部分空間の直和を表す。[証明]
Cayley-Hamiltonの定理より、任意の正方行列Aについて、
が成り立つので、
である。ψ(A)の各因子(A−λi)miを、
と表すことにすれば、
とかける。
と分けて考えれば、A1とA2A3・・・Akは、互いに素な行列多項式で可換である。従って補題6)より、
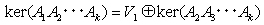
と分解できる(V1=ker(A1))。同様に、
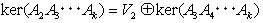
が成り立つ(V2=ker(A2))。同じ分解を、(k-2)回繰り返せば、
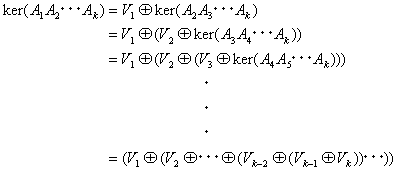
が得られる。V=ker(ψ(A))=ker(A1A2・・・Ak)に注意すれば、
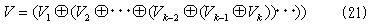
となる。(21)において、ベクトル和は可換なので、
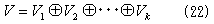
が得られる。
[証明終]

| NO.1547 | 2005.7.24. | 夜ふかしのつらいおじさん | オイラー関数(2) |
問題1
(1)φ(n)=8 を満たす自然数nは、 15,16,20,24,30
- 直接8として
φ(16)=φ(24)=24−23
- 2×4として
φ(15)=φ(3・5)=φ(3)・φ(5)=2・4 (2,4直接)
φ(20)=φ(22・5)=φ(22)・φ(5)=(22−2)・4 (2の変形)
φ(24)=φ(23・3)=φ(23)・φ(3)=(23−22)・2 (4の変形)
φ(30)=φ(2・3・5)=φ(2)・φ(3)・φ(5)=1・2・4 (φ(2)=1利用)
(2)φ(n)=20 を満たす自然数nは、25,33,44,50,66
- 直接20として
φ(25)=φ(52)=52−51
φ(50)=φ(2・52)=φ(2)・φ(52)=1・(52−51) (φ(2)=1利用)
- 2×10として
φ(33)=φ(3・11)=φ(3)・φ(11)=2・10 (2,10直接)
φ(44)=φ(22・11)=φ(22)・φ(11)=(22−21)・10 (2変形)
φ(66)=φ(2・3・11)=φ(2)・φ(3)・φ(11)=1・2・10 (φ(2)=1利用)
※ φ(k)=P(Pは2以外の素数)となる自然数kは存在しない。
Pが素数なので性質(3)(4)は当てはまらない。
(性質の式の右辺が合成数なので)
また、性質(2)も(P+1)は合成数になり当てはまらない。
だから、(2)で 20=4×5 などの可能性はない。
問題2:
100=22×52 である。
だから、100と互いに素な自然数は、2の倍数でなく、かつ5の倍数でない数である。
(1)100より小さくて、100と互いに素な自然数Mの個数は40個。
- 2の倍数は、100÷2=50 個
- 5の倍数は、100÷5=20 個
- 10の倍数(2かつ5の倍数)は、100÷10=10 個
よって、100−(50+20−10)=40個
(2)100より小さくて、100と互いに素な自然数Mの和は2000。
- 1から100までの自然数の和は、(1/2)・100・(1+100)=5050
- 1から100までの2の倍数の和は、(1/2)・50・(2+100)=2550
- 1から100までの5の倍数の和は、(1/2)・20・(5+100)=1050
- 1から100までの10の倍数の和は、(1/2)・10・(10+100)=550
よって、5050−(2550+1050−550)=2000。
問題3:
(1)20のすべての正の約数dについて、φ(d)の値を合計すると,20
(2)100のすべての正の約数dについて、φ(d)の値を合計すると,100
(3)自然数nのすべての正の約数dについて、φ(d)の値を合計すると,n
説明はどれでも同じなので、100でやってみる。
100=22×52 と素因数分解される。
すると、100 の約数は、次の展開の各項である。
| (1+2+22)・(1+5+52) | |
| = | 1・1+1・5+1・52+2・1+2・5+2・52+2 2・1+22・5+22・52 |
その値を引数とする、オイラー関数の和を調べる。
ここで、関数の引数は互いに素な2つの数の積になっている。
また、φ(1)=1 を使う。
| φ(1・1) +φ(1・5) +φ(1・52)
+φ(2・1) +φ(2・5) +φ(2・52)
+φ(22・1)+φ(22・5)+φ(22・52) (性質(4)より) | |
| = | φ(1)・φ(1) + φ(1)・φ(5) +φ(1)・φ(52) +φ(2)・φ(1) + φ(2)・φ(5) +φ(2)・φ(52) +φ(22)・φ(1)+φ(22)・φ(5)+φ(22)・φ(52) |
| = | φ(1)・{φ(1)+φ(5)+φ(52)} + φ(2)・{φ(1)+φ(5)+φ(52)} +φ(22)・{φ(1)+φ(5)+φ(52)} |
| = | φ(1)+φ(2)+φ(22)}・{φ(1)+φ(5)+φ(52)} (性質(3)より) |
| = | {1+(21−20)+(22−21)}・{1+(51−50)+(52−51)} |
| = | 22・52 |
| = | 100 |

| NO.1548 | 2005.7.24. | 佐野允信 | オイラー関数(3) |
問題1
n=2k(kは正の整数)のとき
φ(n)=2k−2k-1=2k-1(2−1)=2k-1 ・・・(1)
n=2l+1(lは正の整数)のとき
n=p1l1・p2l2・・・pmlm
(l1、l2、・・・、lmは正の整数;p1、p2、・・・、pmは奇素数;p1<p2<・・・<pm) ・・・(2)
と表せる。pk(k−1,・・・,m)は奇数だから、
pk=2Sk+1(Skは正の整数;k=1,2,・・・,m) ・・・(3)
と表せる。よって、
φ(n)=p1l1-1(p1−1)・p2l2-1(p2−1)・・・pmlm-1(pm−1)
=2mS1S2・・・Sm
p1l1-1・p2l2-1・・・
pmlm-1 ・・・(4)
従って、n=2l+1(lは正の整数)のとき、φ(n)は偶数である。
(1)
(i)n=2k(kは正の整数)のとき
φ(n)=2k-1 (∵(1)より)
=23 ・・・(5)
∴ k=4
∴ n=24=16 ・・・(6)
(ii)n=2l+1(lは正の整数)のとき
φ(n)=2mS1S2・・・Sm
p1l1-1・p2l2-1・・・
pmlm-1 (∵(4)より)
=23 ・・・(7)
従って、1≦m≦3でなければならない。
(ア)m=1のとき
φ(n)=2S1p1l1-1=23
∴ S1=22 かつ l1=1 ・・・(8)
このとき、
p1=2S1+1=9
となり、p1が素数であることに矛盾する。
(イ)m=2のとき
φ(n)=22S1S2・ p1l1-1・p2l2-1 =23
∴ l1=l2=1 かつ S1S2=2
S1<S2より、(S1,S2)=(1,2) ・・・(10)
このとき、
p1=2S1+1=3
p2=2S2+1=5
となり、p1、p2は奇素数になる。
∴ n=p1l1・p2l2=3×5=15 ・・・(11)
(ウ)m=3のとき
φ(n)=23S1S2S3・ p1l1-1・p2l2-1 ・p3l3-1 =23
∴ l1=l2=l3=1 かつ S1S2S3=1 ・・・(12)
S1S2S3=1より、 (S1,S2,S3)=(1,1,1)となり、 S1<S2<S3に矛盾する。
(iii)n=2k(2l+1)(k,lは正の整数)のとき
φ(n)=φ(2k)φ(2l+1)
=2k-1・φ(2l+1)
=23
φ(2l+1)は、偶数だから、0≦k−1≦2、すなわち、1≦k≦3でなければならない。
以上(i)〜(iii)より、φ(n)=8を満たす自然数nは、(ア)k=1のとき
φ(2l+1)=23 ・・・(14)
(11)より、2l+1=15 ・・・(15)
∴ n=2×15=30 ・・・(16)
(イ)k=2のとき
φ(2l+1)=2mS1S2・・・Sm p1l1-1・p2l2-1・・・ pmlm-1 (∵(4)より)
=22 ・・・(17)
従って、1≦m≦2でなければならない。
(a)m=1のとき
φ(2l+1)=2S1p1l1-1=22
∴ S1=2 かつ l1=1 ・・・(18)
このとき、
p1=2S1+1=5
となり、p1は奇素数になる。
∴ 2l+1=p1l1=5 ・・・(19)
∴ n=22・5=20 ・・・(20)
(b)m=2のとき
φ(2l+1)=22S1S2 p1l1-1・p2l2-1 =22
∴ l1=l2=1 かつ S1S2=1 ・・・(21)
S1S2=1より、(S1,S2)=(1,1)となり、 S1<S2に矛盾する。
(ウ)k=3のとき
φ(2l+1)=2mS1S2・・・Sm p1l1-1・p2l2-1・・・ pmlm-1 (∵(4)より)
=2 ・・・(22)
従って、m=1でなければならない。
φ(2l+1)=2S1p1l1-1=2
∴ S1=1 かつ l1=1 ・・・(23)
このとき、
p1=2S1+1=3
となり、p1は奇素数になる。
∴ 2l+1=p1l1=3 ・・・(24)
∴ n=23・3=24 ・・・(25)
n=15,16,20,24,30 ・・・(答)
である。
(2)φ(n)=20=22×5 ・・・(26)
(i)n=2k(kは正の整数)のとき
φ(n)=2k-1 (∵(1)より)
=22×5 ・・・(5)
となり、矛盾する。
(ii)n=2l+1(lは正の整数)のとき
φ(n)=2mS1S2・・・Sm
p1l1-1・p2l2-1・・・
pmlm-1 (∵(4)より)
=22×5 ・・・(27)
従って、1≦m≦2でなければならない。
(ア)m=1のとき
φ(n)=2S1p1l1-1=22×5
∴ S1p1l1-1=2×5
∴ (S1,p1l1-1)=(2,5)、(10,1) ・・・(28)
(a)S1=2 かつ p1l1-1=5のとき
p1=2S1+1=5
となり、p1は奇素数になる。p1l1-1=5より、l1=2
n=p1l1=52=25 ・・・(29)
(b)S1=10 かつ p1l1-1=1のとき
p1=2S1+1=21
となり、p1が素数であることに矛盾する。(イ)m=2のとき
φ(n)=22S1S2・ p1l1-1・p2l2-1 =22×5
∴ S1S2・ p1l1-1・p2l2-1 =5 ・・・(30)
S1<S2より、S1=1,S2=5 かつ l1=l2=1 ・・・(31)
このとき、
p1=2S1+1=3
p2=2S2+1=11
となり、p1、p2は奇素数になる。
∴ n=p1l1・p2l2=3×11=33 ・・・(32)
(iii)n=2k(2l+1)(k,lは正の整数)のとき
φ(n)=φ(2k)φ(2l+1)
=2k-1・φ(2l+1)
=22×5 ・・・(33)
φ(2l+1)は、偶数だから、0≦k−1≦1、すなわち、1≦k≦2でなければならない。
(ア)k=1のとき
φ(2l+1)=22×5 ・・・(34)
(11)より、2l+1=25,33 ・・・(35)
∴ n=50,66 ・・・(36)
(イ)k=2のとき
φ(2l+1)=2mS1S2・・・Sm p1l1-1・p2l2-1・・・ pmlm-1 (∵(4)より)
=2×5 ・・・(37)
従って、m=1でなければならない。
φ(2l+1)=2S1p1l1-1=2×5
∴ S1p1l1-1=5
∴ (S1,p1l1-1)=(1,5)、(5,1) ・・・(38)
(a)S1=1 かつ p1l1-1=5のとき
p1=2S1+1=3
となり、3l1-1=5を満たすl1は存在しないので矛盾する。
(b)S1=5 かつ p1l1-1=1のとき
p1=2S1+1=11
となり、p1は奇素数となる。p1l1-1=1より、 l1=1
∴ 2l+1=p1l1=11 ・・・(39)
∴ n=22×11=44 ・・・(40)
以上(i)〜(iii)より、φ(n)=20を満たす自然数nは、
n=25,33,44,50,66 ・・・(答)
である。
問題2
(1)100を素因数分解すると、
100=22×52
となる。1から100までの自然数のうち、2の倍数、5の倍数、10の倍数の個数はそれぞれ50個、20個、10個である。従って求める個数は、
100−(50+20−10)=40 ・・・(答)
(別解)
求める個数は、φ(100)である。
∴ φ(100)=φ(22×52)
=φ(22)φ(52)
=(22−2)(52−5)
=40 ・・・(答)
(2)1から100までの自然数のうち、2の倍数の和、5の倍数の和、10の倍数の和をそれぞれ、
S1、S2、S3とおくと、
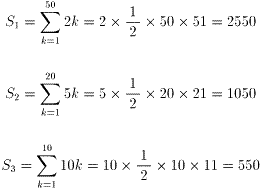
である。1から100までの自然数の和をSとおくと、
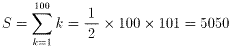
である。従って、求める数は、
S−(S1+S2−S3)=5050−(2550+1050−550)
=2000 ・・・(答)
問題3
(3)
n=p1l1p2l2・・・pmlm
(l1,l2,・・・,lmは正の整数;
p1,p2,・・・,pmは素数;
p1<p2<・・・<pm)
と表すと、nの約数は、
p1α1p2α2・・・pmαm
(0≦α1≦l1,0≦α2≦l2,
0≦αm≦lm
;α1,α2,・・・,αmは整数)
と表せるので、求める数をNとおくと、
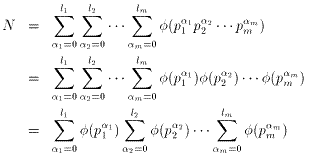
となる。また、
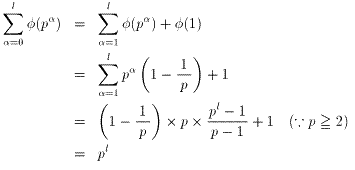
より、
N=p1l1p2l2・・・pmlm=n ・・・(答)
問題3の(3)の結果から、求める数は、20 ・・・(答)
問題3の(3)の結果から、求める数は、100 ・・・(答)

| NO.1549 | 2005.7.24. | 水の流れ | 不思議な平方根 |
皆さん、今年の大学入試を眺めていたら、東京大学で、こんな問題がでていました。これを問題にします。
問題1:3以上9999以下の奇数で、a2−aが10000で割り切れるものをすべて求めよ。
そこで、こんな問題を考えました。
問題2:整数Nにおいて、正の平方根√Nが1桁の整数になり、Nの下1桁と同じになるNを求めよ。
問題3:整数Nにおいて、正の平方根√Nが2桁の整数になり、Nの下2桁と同じになるNを求めよ。
問題4:整数Nにおいて、正の平方根√Nが3桁の整数になり、Nの下3桁と同じになるNを求めよ。
問題5:整数Nにおいて、正の平方根√Nが4桁の整数になり、Nの下4桁と同じになるNを求めよ。
参考: この整数Nを覚えていて、生徒が持っている計算機の画面に入力をします。下1,2、3,4桁を変えなでように画面のボタンをワンタッチで操作してください。どのボタンを操作したら良いでしょうか。
注)この記事に関する投稿の掲載は、8月15日以降とします。

 E-mail
E-mail
 戻る
戻る